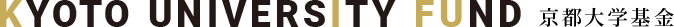Vol.5 教員からのメッセージ
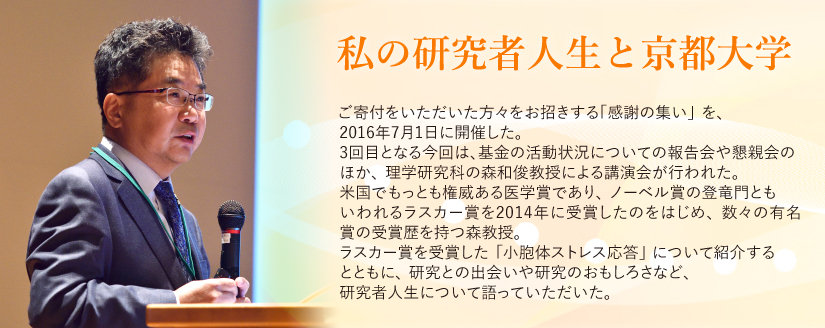
森 和俊 理学研究科教授
MORI KAZUTOSHI 1958年岡山県倉敷市生まれ。1981年京都大学薬学部卒業。1983年京都大学大学院薬学研究科修士課程修了。1985年京都大学大学院薬学研究科博士後期課程退学。1987年京都大学薬学博士。1985年岐阜薬科大学助手。1989年米国テキサス大学博士研究員。1993年株式会社エイチ・エス・ピー研究所副主任研究員、1996年株式会社エイチ・エス・ピー研究所主任研究員。1999年京都大学大学院生命科学研究科助教授。2003年京都大学大学院理学研究科教授、現在に至る。
Awards and honors
1997年 日本生化学会奨励賞
2005年 第4回ワイリー賞
2006年 日本生化学会第1回柿内三郎記念賞
2008年 第26回大阪科学賞
2009年 カナダガードナー国際賞
2010年 紫綬褒章
2012年 平成23年度上原賞
2014年 2013年度朝日賞、ショウ賞、ラスカー賞※
2015年 トムソン・ロイター引用栄誉賞
2016年 恩賜賞・日本学士院賞
※ラスカー賞
正式名称は「アルバート・ラスカー基礎医学研究賞」。アメリカのノーベル生理学・医学賞とも呼ばれるアメリカでもっとも権威のある医学賞。森教授をはじめ過去に7名の日本人が受賞しており、そのうちの2名、利根川進氏と山中伸弥氏がノーベル賞を受賞している。
夢を叶えるのに必要な5つのことと
3つの幸運な出会い
講演機会の多い森和俊教授は、自らの夢を叶えるために必要なこととして次の5つを挙げる。
Ambition(大志)/ Preparation(準備)
Challenge(挑戦)/ Patience(辛抱)
Health(健康)
すべての始まりは大志を持つことであり、実現に向けて準備も挑戦もするし、時には辛抱もしなければならない。でも、これらは心と体が健康であってこそできるものであるという。
「この5つに加えて、私の研究者人生にあった3つの幸運な出会いについて紹介したいと思います」。
小学生の頃は理系少年で、研究者になりたいと思っていた。これが、人生最初の大志である。新聞から科学に関する知識を得ていたが、最初に興味を持ったのが「素粒子物理学」だった。話題になっていたクオークについて、物質をつくる基本粒子のクオークも、さらに小さいものからつくられているのだろうか、と素朴な疑問を抱いた。
1973年、森教授が中学3 年生の時、小林誠博士と益川敏英博士がクオークは全部で6 種類あると予測。ちなみに、その説は後に裏付けられ、両博士はノーベル物理学賞を受賞している。
「日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹博士、2人目の朝永振一郎博士がともに京都大学理学部の出身であることを知り、京大理学部に入学して物理学を勉強したいと思うようになりました」。
森教授の2 番目の大志だ。しかし高校3年生になって、過去問題集などを解いてみると、京大理学部の合格ラインには届く時と届かない時がある。現役合格にこだわった森教授は工学部合成化学科に志望を変更し、合格した。

最初の幸運な出会いは
「分子生物学」
「大志が叶わず、妥協をしたことで、少し後悔のある現役合格でした。入学後はあまり勉強に身が入らず、剣道ばかりしていました」。
そんな森教授を変えたのが、1977年、大学1年生の時に新聞に掲載された利根川進博士らによる「分子生物学」という未知なる学問だ。
「これが最初の幸運な出会いです」。
分子レベルつまり細胞以下のレベルで生命現象を解明しようとする分子生物学は、遺伝子情報が大腸菌からヒトまで共通であることを明らかにした。その登場に衝撃を受け、暗記科目だからつまらないと毛嫌いしていた生物学にがぜん興味を持った森教授は、生物学分野に進もうと、2 年生から薬学部に転入部する。
山科郁男教授の研究室に進み、川嵜敏祐先生の手ほどきを受けて、生化学の研究を始める。薬学部では分子生物学を専門にしている先生はいなかったからだ。「生化学の研究を経験したことが、今の研究に至る準備になりましたね。それに、研究はとにかくおもしろかった」。
答えのない問題に全知全能を注いで挑む研究者の仕事に魅せられた森教授は、研究の世界で生きていくことを決意する。しかし当時、大学に残ることは難しく、博士課程を修了しても就職できないオーバードクターがたくさんいた。悩んでいた時、山科教授のもとで助教授をしていた林恭三先生が岐阜薬科大学の教授に就任する際に誘われ、森教授は博士課程を2年で中退し、1985年に岐阜薬科大学の助手となる。
岐阜薬科大学で手がけたのも、やはり生化学分野の研究だったが、念願の大学教員というポストで、「論文をたくさん書きなさい」という林先生の方針のもと、4年間で8本もの論文を発表した。ただ、次第に当時の研究分野にはもう発展はないと感じるようになった森教授。別の研究を進言するが、聞き入れてもらえなかった。
ここで、森教授は大きな挑戦をすることになる。「研究に苦労はつきもの。どうせ苦労するなら、もっとおもしろいこと、重要なこと、発展性のあることをしたい」と、大学教員を辞すことにしたのだ。
2番目の幸運な出会いは
「小胞体ストレス応答」分野
「研究がうまくいかないのは環境のせいなのか、自分の能力の限界なのか、見極めよう」。
分子生物学の本場・米国を目指したものの、なかなか受け入れ先が見つからず、ようやく決まったのが米国テキサス大学のサムブルック教授、ゲシング教授の研究室だった。
本音としては、2年ほど英語と分子生物学を学んで東海岸か西海岸へ行こうという気持ちだったが、図らずもこの研究室で現在の研究テーマである「小胞体ストレス応答」と出会う。これが2つめの幸運な出会いだ。
森教授が留学した1989年の前年、両教授が小胞体ストレス応答の存在を報告したばかりだった。「その研究に最初から携わることができたのも、思い切って渡米したから出会えた幸運でした」。
自分の研究遂行能力は高いことがわかった、と笑う森教授。
「諦めなくてよかった。人間万事塞翁が馬。どこかに自分の場所はある。悲観する必要はありません」。
細胞が持つ驚異の復元力
「小胞体ストレス応答」
「小胞体ストレス応答」は、言い換えれば「タンパク質の品質を管理する細胞応答」である。生物体を構成する細胞の中では、たくさんの細胞内小器官が集まってそれぞれの機能を分業しているのだが、この細胞内小器官の1つが「小胞体」である。網目状の膜状構造で、タンパク質合成などの機能を持つ、いわば"工場"だ。
小胞体内で、タンパク質はアミノ酸が数珠つながりになった紐状の形で合成され、それぞれの役割を果たすために適した立体構造を形成していく。タンパク質は本来、自然に立体構造をとる能力を持っているが、小胞体内に存在する「シャペロン」というタンパク質が成形を介助する。ちなみに、「シャペロン」とは、フランス語で「介添え女性」の意味である。
シャペロンの介助があっても、時には不良品のタンパク質ができてしまうのだが、通常の工場が製造だけでなく製品の品質管理もするように、小胞体も同じことをしているという。
「小胞体は不良品のタンパク質を判別して、これを修復しようとするんです」。
さまざまな環境変化により小胞体内部の状態がおかしくなることがある。不良品タンパク質が増えすぎたり、良いものが悪いものに変わってしまうこともある。小胞体に負荷のかかった状態が「小胞体ストレス」だが、こういう時でも細胞はストレスを克服して、恒常性を保つ機構を備えている。これが「小胞体ストレス応答」だ。
具体的な応答としては、小胞体内に不良品タンパク質が溜まってくると、その情報を核に伝え、シャペロンの数を増やして、タンパク質を成形する能力を高める。同時に、不良品タンパク質を分解処分するための「引き抜き装置」の数も増やして、タンパク質の分解能力もアップさせるのである。
「小胞体ストレス応答」の仕組みを
解明する3つの仮説に挑む
小胞体ストレス応答の仕組みはどうなっているのか? 解明にあたり、森教授は3つの仮説を立てた。
まず1つめは、小胞体の状況を監視する" 目"のようなものがあるはずだ、という説。テキサス大学の教授のアドバイスで、酵母の小胞体を使い、この目が働いているかどうかチェックした細胞は実に10万個。ついに、不良品タンパク質が溜まったことを感知するセンサー分子・IRE1を発見した。
「1993 年、私の最初の出世作です」。
論文発表のタイミングは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のピーター・ウォルター教授に先を越されたが、森教授の論文のほうが内容が詳細だったことから、2カ月遅れて同じ科学誌に発表されている。
3番目の幸福な出会いが
その後の研究に弾みをつけた
2つめの仮説は、小胞体に不良品タンパク質が溜まってきた時、シャペロンの数を増やす仕組みがあるはず、というものだ。
センサー分子の発見後、森教授は帰国して、京大ウイルス研究所長だった由良隆教授が産官共同プロジェクトとして京都に設立したエイチ・エス・ピー(HSP)研究所の研究員に就任。引き続き、酵母での研究を進め、核のDNAにシャペロンをつくることを働きかける転写因子HAC1の発見に至った。
「7年という研究所の時限の中で成果を出せるよう、目的のタンパク質だけが得られる方法を考えなさい」という由良先生のアドバイスを受け、2年がかりの苦労の末に思いついたのが、「ワンハイブリッド法」という方法だ。
「これが3 番目の幸運な出会いです」。
同法が、哺乳類を対象にした小胞体ストレス応答の解明に大いに役立ったのである。
3つめの、小胞体と核をつなぐ仕組みがあるはず、という仮説も、IRE1とHAC1との間が新奇な機構でつながれていることを解明している。
「仮説2と3の研究においても、ピーター・ウォルター教授との激しい競争があり、死闘と呼ばれたりしました。でも、じっと辛抱して研究に専念し、競争に勝つことができました」。

目標に到達する道はらせん状
あきらめず前に進もう
HSP研究所の終了1年前の1999年、折しも京都大学に新しく生命科学研究科が設置されることになり、助教授の職を得る。森教授は14年ぶりに京大に戻ってきたわけだ。
哺乳類に対象を移していた森教授は、HSP研究所で自らのチームに参加してもらっていた京大出身の吉田秀郎氏(現・兵庫県立大学教授)と共に、京大で研究を続け、1999年に哺乳類でのセンサー分子、2001年に小胞体と核をつなぐ経路を発見。
「1993年以降、次々に結果が出るという、夢の10年間でした。彼といい由良先生といい、すばらしい人々に恵まれたおかげです」。
そして2003年、理学研究科生物科学専攻生物物理学教室の教授が公募され、森教授が着任、現在に至っている。
生物物理学は、シュレーディンガーという物理学者が1944年に物理学的観点から生物を考察した講義で話題となって以降、広まった学問分野。現代でも引き継ぐのは、京大の同教室のみである。
「学生として入ることができなかった京大理学部に、教員として入ることができました。物理好きから分子生物学へという道を歩んできた私にとって、生物物理学教室はまさに理想でした」。
現在も精力的に研究に取り組む森教授。「おもしろいのは、高等動物ほど小胞体ストレスに対して、より巧妙で多重な備えが用意されていることですね」。酵母にはセンサー分子も転写因子も1つしかないが、哺乳類になるとセンサー分子は3つになるという。
「タンパク質の異常にうまく対応できなければ、進化できなかったのでしょう」。仕組みが複雑になった境目は背骨ができた時だと考える森教授は、現在、メダカを対象にした解析も進めている。
最終的に目指すのは、小胞体ストレス応答と病気の因果関係を突き止めること。「小胞体ストレスが関与していると考えられる疾患の発症機構を解明し、予防や治療に道を開きたい」。
大志を持って準備、挑戦、辛抱し、それを支える健康を、中学から続けている剣道で培ってきた森教授。「1989年に大学助手を辞めてから綱渡りの人生でしたが、一生懸命努力をしているといろいろな人が助けてくれました」。
最後に、森教授は「特に若い人たちへ」と、こんなメッセージで締めくくった。「目標に向かって一直線に進むことは難しい。私もまっすぐ突き抜けてきたわけではありません。でも我々のDNAは二重らせんです。回り道のようであっても前へ前へと進んで行けば、いつかはゴールにたどり着きます。ですから、上を向いていきましょう」。
【講演こぼれ話】
2016年3月に恩賜賞・日本学士院賞を受賞した森教授は、天皇皇后両陛下がご陪席された授賞式、皇室の方々とお食事をした時の様子など貴重な体験談を披露しました。
また、「研究ばかりしていると思われがちですが、ちゃんと講義もしてますよ」と森教授。講演会の前にも90分講義を終えてきたばかりで、年間の講義は50回ほどだそう。「どうすれば学生に寝られず、満足してもらえるか。今もって苦労しつつ、いろいろと工夫をしています」。工夫の成果をまとめたのがこの1冊と、紹介したのが『細胞の中の分子生物学』。「ネット通販の売れ筋ランキングもチェックしていて、ずっと上位をキープしています」と、自著を売り込んで笑いを誘いました。