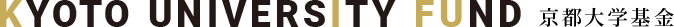FINISHED
終了したプロジェクト支援基金
宇治キャンパス環境整備等基金
京都大学宇治キャンパスは1947(昭和22)年に活動を始め、現在は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所、防災研究所の4研究所を中心に、学生約940名、教職員約780名が自然科学系の最先端の教育・研究活動を展開しています。
また、おうばくプラザ周辺は地域住民も自由に立ち入りできる憩いの場として親しまれ、宇治キャンパス公開等を通じて、研究成果の社会への発信を図っています。
さらに、宇治キャンパス産学交流会等を通じて、研究者と企業間の情報交換、連携を促進し、産学連携の拠点にもなっています。本基金は、宇治キャンパスの教育・研究に資する設備および環境の整備や宇治キャンパス公開、たそがれコンサート等の地域交流行事の開催、地方公共団体等との協賛事業の実施に使用していきます。
桂図書館基金
桂図書館基金は、教育・研究支援、環境向上支援、若手研究者支援を目指し、2020(令和2)年度の桂図書館開館にあわせて設置しました。お寄せいただいた寄付金で実施した事業内容は以下の通りです。
・環境向上支援事業:2021(令和3)年度に設置した「長尾文庫」の銘板を作成しました。この文庫は、長尾真京都大学元総長・名誉教授から寄贈を受けた旧蔵書約5,000冊からなる幅広い分野のコレクションで、閲覧室の壁一面に配架し、利用者の教養の涵養に寄与しています。
・若手研究者支援事業:研究成果発信支援事業公募により、2023(令和5)年度に工学研究科・小見山陽介講師の応募を採択し、桂図書館を会場とした展覧会「ヴォイスオブアースデザイン小委員会展 京都巡回展」を開催しました。これは、日本建築学会が東京で実施した展覧会の巡回展で、桂図書館の1階と2階を会場に、ポスター、建築模型やドローイングを展示しました。学外からの来訪者も多く、桂図書館の大きなアピールにもなりました。
桂図書館基金は2025(令和7)年6月末をもって特定基金としての取り扱いを終了しましたが、お寄せいただいた基金は当初の目的に沿って活用し、寄付者の皆様のご厚志に応えたいと考えています。これまでのご支援に心から御礼を申し上げます。
先端光・電子デバイス創成学卓越大学院基金
本卓越大学院では、独創力、俯瞰力、挑戦力、国際力、自立力の5つの力を兼ね備え、高度に専門的な知識と技術、強い責任感と倫理性を身につけた人材、「先端光・電子デバイス学」を創成する国際的な知のプロフェッショナルとして世界でこの分野を牽引できる人材を育成するために以下の事業を行いました。
◇研究科の壁を越える共通基盤科目「先端光・電子科学の展望」の開講
◇学生が有する優れたアイデアと技術を、海外を含む連携機関等で発展させ、学理の深化/社会実装を加速させるための武者修行「フィールド・プラクティス」の実施
◇理・工・情報の3研究科の壁を越える異分野の研究室で短期研究を行う「研究室ローテーション」の実施
◇研究科の壁を越える切磋琢磨の取り組みとして「国際セミナー道場」、「国際シンポジウム」の実施 ※機構SPRINGプログラム(量子分野)との共同開催
◇学生の自由な発想に基づく独自性の高い研究提案に対する競争的研究費「研究グラント」の実施
◇履修生のつながり促進や基盤育成活動としての「e-卓越カフェ」、「e-卓越セミナー(社会システムセミナー)」の実施
◇学内外の卓越大学院や教育プログラムとの連携
大学院横断教育プログラム推進基金
寄付募集活動については、これまで十分に実施できていませんでしたが、今後も、本学大学院における横断教育の推進と履修者支援を行うとともに、広く産官学にわたりグローバルに活躍できる人材の育成を目指します。
宇治川オープンラボラトリー基金
2024(令和6)年度は、セミナー室におけるプロジェクターの更新工事を実施し、見学者や研究参加者に対する講義・説明環境の向上を図りました。これにより、教育的な活用の質が一層高まっています。また、洪水流実験装置の第1観測室では、屋上防水の改修工事を行い、実験施設としての安全性・耐久性を確保し、安定した研究環境の整備に寄与しました。これらの取り組みにより、施設の維持管理および研究・教育活動の円滑な実施が支援できています。過年度には、宇治川オープンラボラトリーの電気代への振替や、水路周辺の樹木伐採・撤去作業にも基金を活用しており、施設全体の安全性と機能性の向上に資する支出を行っています。
グローバル生存学基金
現代社会では、巨大自然災害、突発的人為災害・事故、環境劣化・感染症などの地域環境変動、食料安全保障といった危険事象や社会不安がますます拡大しています。これら社会の安全安心を脅かすさまざまな事象に対峙するため、あらかじめ対策を講じ、事象発生時には適時・的確に対処できる国際的リーダーの育成が重要です。京都大学では9つの研究科と3つの研究所が協力し、5年一貫の大学院教育プログラム「グローバル生存学大学院連携プログラム」(GSSプログラム)を実施して、「グローバル生存学」という新たな学際領域を開拓し、社会の安全安心に寄与できるグローバル人材を養成しています。2023(令和5)年度からは修士課程のみでも修得可能な「グローバル生存学コース」を立ち上げ、GSSプログラムの目指す社会的俯瞰力を備えた世界の安全と安心に寄与する人材を広く育成します。
今後もこれらの安全安心分野の先進的・学際的な大学院教育の展開に活用していきます。
京大異分野融合基金
頂戴しました基金は、京都大学における学際活動の推進に幅広く活用させていただきました。
今後も引き続き、これまでに実施してきた匿名研究ポスター大会「京大100人論文」、当センター設立当初より15年間毎月開催している「全分野交流会」の開催を継続していくとともに、新規学際的研究教育ユニットの発足支援を実施していきます。
なお、残金に関しては、以下の実施内容に活用させていただきます。
2025(令和7)年度は11月に「京大100人論文」の開催が決定しています。2024(令和6)年度は過去最多となる約850名(本学研究者、地域の方、企業関係者、院生・学生、高校生、小学生を含む)にご来場いただき、過去最多となる約3,000枚の付箋紙でのコメントや質問が交わされました。また、本企画は「京大発モデル」として全国30の学術組織で実施されるなど、注目を集めています。「全分野交流会」は7月と11月に京大にて開催、それ以外の月はオンライン開催を予定しています。毎月30名以上が参加する活発な交流の場となっています。
これらの活動を通じて、研究者同士の出会いの場を創出し、本学の学際活動の活性化に貢献しています。今後も、ご寄付いただいた基金を最大限に活用し、新たな知の創造と社会貢献に努めていきたいと考えています。
アジア研究基金
京都大学東南アジア地域研究研究所は、文理融合・超学際研究の世界的拠点として東南アジア地域研究を牽引してきました。
私たちにとって大切な目標は、アジア諸国の研究者・研究機関との学術パートナーシップを強化し、既成の学問分野を越えた新しい知の枠組みをつくり上げることにあります。特に、若手研究者にとって、自主的に研究調査や交流を実施するための支援体制は未だ十分とはいえません。また、国際的な成果発信が求められる中で、まとまった成果を出版するための支援も限られています。
「アジア研究基金」は、アジア研究に携わる次代を担う若手研究者の研究力強化を目指して、東南アジア地域研究研究所が構築してきた研究交流の国際ネットワークや学術誌・叢書などの研究発表の場を有効に活用して学術交流、人材育成、研究成果の国際発信を進めてきました。
本基金のもとで、アジア研究の学術成果の出版支援として、「東南アジア研究の国際共同研究拠点」<~2022(令和4)年度>および「グローバル共生に向けた東南アジア地域研究の国際共同研究拠点」<2023(令和5)年度~>の公募出版助成を行い、これまでに合計9冊の書籍を刊行することができました。本基金は解散しますが、今後はこの事業は京都大学の一般寄付金を活用して継続していく予定です。これまでのご支援に心より御礼申し上げます。
熱帯林共生基金
本基金にご寄付をいただきありがとうございます。
いただいた資金は熱帯林生態系の保全・修復・再生と、地域社会の持続的発展を目指した研究と実践を展開するために利用いたします。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に、ようやく以前のように自由にフィールドワークができるようになりました。ユニットメンバーがこれまで築いてきたアジア・アフリカ地域の大学・公的機関・NGOや地域社会とのネットワークを活用して、今後の熱帯林生態系の修復・再生と地域社会の持続可能な発展に結びつく、実践的研究活動を進めました。
なお、熱帯林共生基金は、2025(令和7)年度には「特定基金」から「寄付金」へ変更となりますので、京都大学基金ウェブサイトを通した寄付金の募集は終了いたします。
宇宙ユニット基金
宇宙ユニットではこれまで、基金を主に社会連携活動:宇宙総合学に関わる一般向けのアウトリーチ活動と広報の実施に使用してきました。2025年3月末の当ユニットの終了に伴い、当基金も終了する予定です。残金は、シンポジウム等アウトリーチ活動とユニット閉鎖に伴う諸経費に充てる予定です。